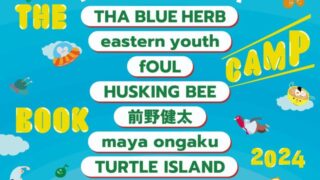火迺要慎(ひのようじん)、火除けの神様として厚く信仰されている「愛宕神社」。現在総本宮は、京都市愛宕山に鎮座しますが、その元祖は亀岡市の「愛宕神社」。そのため「元愛宕」「愛宕の本宮」とも呼ばれています。
集落の奥にひっそりと佇む小さな神社です。華やかさこそありませんが、きれいに整備された境内は人々の多くの信仰を集め大切にされていることを物語ります。
愛宕神社(元愛宕)の歴史・成り立ち・由緒
亀岡の愛宕神社が元祖?
京都府亀岡市に鎮座する「愛宕神社(あたごじんじゃ)」。旧称は「阿多古神社」。

創祀は神代(じんだい)。神武天皇の即位以前の、神々がこの国を支配していた時代に遡り、背後の牛松山を神籬(ひもろぎ)、つまり神の依り代として祀ったのが、創祀と伝わります。社殿の創建は507年 継体天皇元年とのこと。このときが、創祀との説もありますが、いずれにしても、かなりの歴史を持ちます。
平安時代編纂の歴史書『日本三代実録』では、「阿当護神(愛当護神)」として神階が記され、平安時代中期編纂の『延喜式神名帳』では丹波国桑田郡「阿多古神社」として記載が残ります。
その後天武天皇の頃、愛宕神社の分霊が京都「鷹ヶ峰」に勧請され、701~704年に手向山(愛宕山朝日嶽)に遷された後、781年に「和気清麻呂(わけのきよまろ)」と慶俊僧都(けいしゅんそうず)が、社殿を造営遷宮。こちらが、現在の「総本宮 愛宕神社」です。
そのため、亀岡の愛宕神社は、「元愛宕」や「愛宕の本宮」とも称されています。
愛宕山の総本山愛宕神社によると、701〜704年に朝日峰(愛宕山)に神廟を建立が創建、781年に慶俊が中興、和気清麻呂が朝日峰(愛宕山)に白雲寺を建立し愛宕大権現として鎮護国家の道場とした、との縁起があります。
遷されたのか、愛宕山で創建されたのか、、、この違いを証明するほどの資料は今の所見つかっていないそうです。
火伏せの神 愛宕神社

御祭神 「火産霊神 (ほむすびのかみ:軻遇突智神:かぐつちのかみ)」は、神話における火の神様。他にも、鍛冶、防火、陶器、温泉を恵む神格を持つことから、鎮火・防火、火難除け、郷土守護、陶器業・鉱業守護、開運招福、金運向上などのご利益があると信仰されています。
愛宕神社(元愛宕)は、火伏せの神としての信仰が厚く、京都の家々や飲食店には「阿多古祀符 火迺要慎」のお札が貼られているといいます。「伊瀬へ七度、熊野へ三度、愛宕へは月参り」と言われるほどの崇敬です。今でも、4月24日の鎮火災には多くの方が参詣します。
京都では、「愛宕の三つ参り」として、3歳までに参詣すると一生火災に遭わないと昔から信仰を集めています。
愛宕神社 公式サイト:なし
愛宕神社(元愛宕)の御祭神
愛宕神社(元愛宕)の御祭神は三柱です。
愛宕神社(元愛宕)のご利益
- 火除け・災難除け・魔除け
愛宕神社(元愛宕)の見どころ
広い境内ではありませんが、歴史を感じ心静まる神社です。
荘厳な石鳥居

地味ではありますが、まさに「結界」であることを感じる荘厳な石鳥居に迎えられます。
鳥居脇には「本宮 愛宕神社」の社号標。こちらは新しいものですが、あえて「本宮」と彫られてあるところに、神のご意思ではなく、なにか人の思いを感じずにはいられません。
京都市愛宕山に鎮座する、「愛宕神社」は「総本宮愛宕神社」で、現在の全国約900社の愛宕神社の総本宮です。
愛宕神社(元愛宕)の本宮

「本殿」は鎌倉時代後期の1280年(弘安3年)頃の造営、国の重要文化財に指定されています。
八幡宮神社

舞殿奥に鎮座する「八幡宮神社」。御祭神は応神天皇。
天平年間(729年~749年)に、八幡総本宮の宇佐神宮から御祭神 応神天皇を分霊し、丹波国分寺に祀られたと伝わります。国分寺の荒廃により、1835年愛宕神社に遷座し祀られています。
天満宮社

本宮手前、手水舎の横に鎮座するのが「天満宮社」。
手水舎のすぐ横には、撫で牛的な牛が横たわっています。すっかり苔むした牛は、多くの時が流れたことを伝えてくれます。
樹齢1000年とも伝わるご神木

社務所前には樹齢1000年とも伝わるご神木の大スギ。
「ムササビの生息する森」として亀岡の自然100選に選ばれる境内には、たくさんの大木があります。
心あらわれる湧き水
境内には、ただ静かに流れ落ちる湧き水があります。地形上近くまで寄ることはできませんが、ただ見ているだけでも心あらわれるようです。
摂末社
境内には、下記摂末社が祀られています。

愛宕神社(元愛宕)の授与品:御朱印、お守りや御札など
授与品
- 各種お守りや、お札、御朱印は、授与所でいただくことができます
- 火迺要慎(ひのようじん)のお札もあります
- 授与所にはどなたもいらっしゃなない場合が多いのでご注意ください
インターネット販売
- 授与品はインターネットでの販売はありませんので、ご注意ください
▼お守りが必要な方のあいだで話題の”最強の護符”については、下のサイトが詳しいです。

愛宕神社(元愛宕)の拝観料・参拝時間、所要時間、アクセス情報、駐車場情報など
拝観料
- 無料
参拝時間
- 境内参拝時間:自由
授与所で、御札やお守り等いただけますが、誰もいないことの方が多い(特に平日)のでご注意ください。社務所前ホワイトボードに予定が記載されています。
所要時間
- 15分程度
アクセス情報
◆JR山陰本線(嵯峨野線)亀岡駅下車
・亀岡市ふるさとバス JR千代川駅行 F11系統 「国分」下車 徒歩5分程度
・タクシー10分程度
・徒歩40分程度
・ 亀岡市ふるさとバス 時刻表 ← 本数がとても少ないです。時間を確認の上ご利用ください。
・ 亀岡駅でタクシーを拾うことはできますが、愛宕神社(元愛宕)近辺の道路で拾うことは、ほぼ無理です。タクシーご利用の場合には、駅から利用し、参拝中も待っていただくことをおすすめします。
駐車場
- 普通車 無料
- 境内入口付近に無料駐車場がありますが、道路は細く坂道ですので、ご注意ください。
愛宕神社(元愛宕) 近くパワースポット
布袋尊だらけ 養仙寺

愛宕神社から徒歩1分の距離にある「養仙寺」。
- 臨済宗妙心寺派の寺院
- 山号は福智山
- ご本尊は地蔵菩薩、
- 丹波七福神めぐりの第二番の札所

大小新旧さまざまな布袋尊が600体ほど安置されています。
創建は天平13年(741)とも寛正年間(1460~1466年)とも云われますが、いずれにしても古寺です。

度重なる兵火や、明智光秀の侵攻で衰退したものの、1639年に再興され臨済宗に改宗。
ご本尊の木造地蔵菩薩立像は、平安時代末期から鎌倉時代初期に制作され、足利尊氏の念持仏と伝わります。当初はお隣の「愛宕神社」の本地仏として祀らていましたが、明治時代の神仏分離令後に養仙寺に移されたとのこと。
出雲大神宮:1300年の歴史を誇る「縁結び神社」
・亀岡神社(元愛宕)から「出雲大神宮」までは、徒歩30分ほどかかります。
・亀岡神社近く(バス停:国分)から出雲大神宮までのバス(亀岡市ふるさとバス:F11系統)はありますが、本数がかなり少ないので注意が必要です。
・出雲大神宮⇔亀岡駅はバスがあります。本数は少ないですが、バス時間にあわせて境内を拝観すれば特に困るようなことはありません。
おすすめの宿
亀岡駅周辺には、ホテルは多くありません。前後の移動や食事、観光を考えると京都市内での宿泊がおすすめです。
おすすめの駅はJR「二条駅」。JR嵯峨野線(各駅停車、特急いずれも乗車可能)にも乗れますし、観光や移動にも便利です。
JRでの移動の場合には、JR嵯峨野線で京都駅ー亀岡駅は、特急で20分弱、普通電車でも30分程度です。
旅先での宿泊こだわり検索リンク集
ホテルや旅館を自分で探したい場合は以下のリンクが近道です。※楽天トラベル内にリンクします。
👉もし、どの宿(ホテル)も予約でいっぱいの場合はこちらの記事が参考になります。